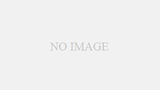賃上げ促進税制とは、賃上げや人材育成などの投資を積極的に行う中小企業が活用できる可能性のある、税額控除を受けられる制度のことです。
今回は、「賃上げ促進税制」の活用する際に知っておくべきことについて、解説していきたいと思います。
制度の概要について
賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業などが、従業員の前年度給与などを一定以上増加させた場合、増加額の一部を法人税から税額控除できるという制度のことをいいます。
中小企業向けの制度の対象企業は、以下のような条件を満たしている企業です。
- 青色申告書を提出している
- 資本金または出資金の額は1億円以下の法人
- 従業員数が1000人以下の法人や個人事業主
- 中小企業など協同組合や出資組合の商工組合などの組合組織
※同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人などは対象外となります。
令和6年(2024年)4月1日開始事業年度以降、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能(新設)となりました。
対象者は中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主です。
5年間の繰越しができるようになったことで、使いやすくなりました。
要件について
適用要件には、通常要件と2つの上乗せ要件があります。
- 通常要件:給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
- 上乗せ要件:教育訓練費の額が前年度と比較し、5%以上増加していて、適用事業年度の教育訓練費が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上
- 上乗せ要件:子育てサポート企業の認定を受けた証である「くるみん」以上または女性活躍推進事業主を示す「えるぼし二段階目以上」の認定を受けている
それぞれ確認していきましょう。
通常要件
制度の活用をするために、最低限満たさなければならない要件となります。
給与支給額の増加率1.5%以上の場合は15%、増加率2.5%以上の場合は30%を法人税額もしくは所得税額から控除することが可能です。
増加率については、「(給与等支給額-比較給与等支給額)÷比較給与等支給額」という計算式で算出できます。
給与等支給額は、賃上げ促進税制を活用したい事業年度で従業員に支給した給与等の支給額の合計のことを指します。
比較給与等支給額とは、前事業年度における給与等支給額のことです。
上乗せ要件
教育訓練費の額が前年度と比較し、5%以上増加していて、適用事業年度の教育訓練費が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上の場合には、税額控除率が10%上乗せされます。
また、子育てサポート企業の認定を受けた証である「くるみん」以上または女性活躍推進事業主を示す「えるぼし二段階目以上」の認定を受けている場合には、税額控除率が5%上乗せされます。
つまり、通常要件と併せて上乗せ要件を活用することで、最大45%もの税額控除を受けられる可能性があります。
制度活用によるメリット
賃上げ促進税制を活用することで、節税効果を得られることが最大のメリットといえます。
従業員の賃上げは会社にとって大きな負担ですが、会社が支払わなければならない法人税に対して、税額控除を受けるといった形で、賃上げによる負担を軽減できる可能性があります。
また、従業員にとって働きやすい労働環境の整備につながり、人材の確保や定着の実現が期待できることがメリットとして挙げられます。
中小企業では人手不足や人材の流出が問題視されているため、賃上げによる労働環境の整備は、人材の定着につなげることが期待できるでしょう。
さらに、上乗せ要件として、教育訓練費の増加が含まれているため、会社は人材育成のための資金を投じやすくなり、従業員のスキルアップの実現をしやすくなる可能性が高まります。
スキルアップを目指せる環境の整備は、結果として、従業員の満足度の向上へとつながり、人材の定着が期待できます。
制度活用の際の注意点
賃上げ促進税制を活用することで得られるメリットの反面、把握しておく必要のある注意点もあります。
制度の活用には、前年度の給与など支払額を増加させていることが条件となるため、前事業年度が存在しない新設企業などは、適用の対象とはなりません。
また、賃上げを行うと、労働保険や社会保険などの保険料負担も増加するため、会社の負担も増えることになるため、計画的に実施しないと資金繰りを悪化させる恐れもあります。
賃上げによって、どれくらい保険料が増加する見込みなのかを事前に確認するなどの準備をしておくことが重要です。
まとめ
今回は、「賃上げ促進税制」の活用する際に知っておくべきことについて確認していきました。
賃上げ促進税制を活用することで、節税効果が得られる上に人材の確保や定着など、会社にとってさまざまなメリットをもたらす可能性があります。
ただし、これらのメリットを最大限に活用するためには、適用要件や上乗せ要件を正確に把握しておくことが必要です。
また、賃上げに伴うさまざまな影響を事前に確認して準備をしていくことや、賃上げの影響に対する経営戦略を練ることも重要です。
賃上げ促進税制の活用について検討している場合には、専門的な知識をもつ税理士へ相談することを検討してみてください。