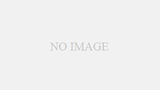決算報告書とは法人が事業年度ごとに作成する書類で、企業の財務状況・経営成績・キャッシュフローの状況を示しています。
法人税法上ではこれらの決算報告書を添付して、確定申告をしなければいけません。
本記事では、法人税法上での決算報告書の提出期限と提出する書類について解説します。
申告期限は原則として各事業年度の2か月後
法人税の確定申告は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内です。
決算日が3月31日の法人であれば、5月31日が申告期限になります。
ただし、申告期限が土日あるいは祝日の場合は、その翌日が期限となります。
法人の事業年度は自由に設定でき、会社の約款で決めておきます。
一般的には3月末が多いですが、繁忙期を避けて決算月を定める会社もあります。
申告期限の延長の特例
法人税の申告は一定の理由があれば、特例として延長が認められています。
延長が認められる理由は大きく分けて2通りあります。
「申告期限の延長の特例の申請書」を提出した場合
会社の運営上による特別な事情がある場合、申告を1カ月延長することができます。
特例を受ける条件は以下の通りです。
- 「申告期限の延長の特例の申請書」を決算日までに税務署に提出する
- 「定時株主総会を事業年度終了後3カ月以内に行う」と定款で定めている
この場合注意すべきポイントは、納付期限は延長されないという点です。
申告期限の延長が認められた場合は、概算の納付額を計算して本来の納付期限までに見込納付をします。
その後納付額を確定し、もし見込納付額を確定納付額が上回ってしまったら、不足分に利子税が課せられることになります。
自然災害などのやむを得ない事情が発生した場合
自然災害などのやむを得ない事情によって申告できない場合があります。
大規模な災害が発生して広い地域で被害が及んだ場合には「地域指定による期限延長」が認められます。
国税庁が地域と期限を定めて実施するので、税務署への申請は必要ありません。
ただし地域指定による期限延長は、納税者が指定地域に納税地を保有している必要があるので気を付けましょう。
たとえば、指定地域に支店があったとしても、納税地は本店がある地域というケースが考えられます。
その場合は地域指定による期限延長の適用を受けられません。
一方で個別に税務署へ申請して申告期限が延長されるものが「個別指定による期限延長」です。
地域指定以外で災害が発生した場合など、延長申請の承認を受けて適用されます。
また災害によって申告延長する場合は、納税期限も延長されます。さらに利子税も免除されます。
決算報告書で提出する書類
次に決算報告書で提出する書類について解説します。
決算書
決算書は主に以下の5つの書類で構成されています。
- 貸借対照表:決算時の資産、負債、純資産の状態を表した書類
- 損益計算書:収益から費用を差し引いた、企業の経営成績を示す書類
- キャッシュフロー計算書:企業の1年間のお金の流れを表した書類
- 株主資本等変動計算書:一事業年度における株主資本の変動項目を示す書類
- 個別注記表:決算書に関する注記をまとめた書類
その中でも「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」は財務三表と呼ばれ、特に重視されています。
しかしキャッシュフロー計算書は、上場企業では作成が義務付けられていますが、中小企業などでは作成義務がありません。
勘定科目内訳明細書
勘定科目内訳明細書は、貸借対照表や損益計算書の勘定科目の内訳を示した書類です。
法人税法施行規則35条で税務署への提出が義務付けられています。
国税庁のホームページより、用紙をダウンロードすることも可能です。
ただし、勘定科目ごとに作成する書類のため枚数が多くなります。
そのため会計ソフトを利用すると、より簡単に作成することができます。
法人事業概況説明書
法人事業概況説明書はその名の通り、法人の事業内容や状況を記載した書類です。
法人名、納税地、事業内容、期末従業員数の状況、主要科目などを記載します。
各種確定申告
法人税、消費税、法人事業税、法人住民税などの税額計算を行った書類です。
税額計算は決算書が完成してから作成するので、作成手順とスケジュールに注意しましょう。
まとめ
決算報告書の作成は、企業にとって年1回の大事な健康診断です。
規模の大小にかかわらず、必ず決算報告書を作成しなければなりません。
また決算報告書を税務署だけでなく、金融機関や株主に提出する企業も多くあります。
作成にあたっては内容にミスが発生しないように注意を払い、期限までにしっかりと提出できるようにスケジュール管理をしましょう。
作成内容が多く複雑な箇所もあるので、不安な場合は税理士に相談することを検討してみてください。